

本記事の内容
- ①先進国の援助総額は増加、日本は伸び悩み
- ②先進国ごとの特徴をまとめてみよう
- ③最近のコロナに対しての各国対応も紹介
本記事の信頼性
記事を書いている私は、プロとして国際協力を仕事にして4年、アマ時代も含めると17年国際協力に携わっています。他の先進国援助機関の状況を常にウォッチしてます。
読者さんへの前置きメッセージ
本記事では「日本以外の先進国って国際協力でどんなことやってるのかざっくり知りたい」という方に向けて書いています。
この記事を通して、各国の国際協力の動向をイメージできるようになると思います。
これだけ世界が多様化する世界で、業界全体の動きを知っておく意味でも各国の国際協力の特徴を知っておくことは重要です。
それでは、さっそく見ていきましょう。
①伝統的先進国の国際協力をざっくり見てみよう
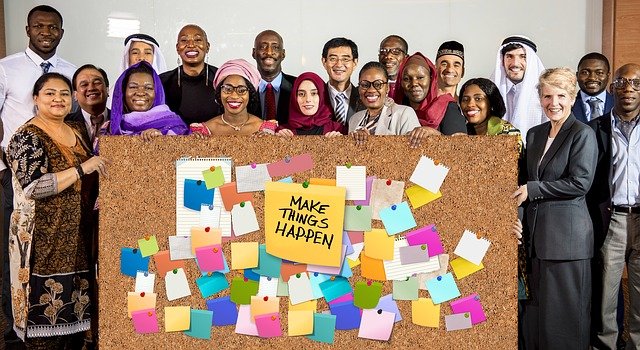
ここでは先進国の国際協力の実績をみていきましょう。
伝統的先進国の援助実績は増加。日本は伸び低迷
ここでは、日本、米国、ドイツ、英国、フランス、イタリア、カナダを数字で見ていきましょう。
伝統的な先進国の 政府開発援助(ODA)は増加していますね。一方、日本の ODA の伸びは低迷してます。
一時、先進国で一番のODA拠出国だったのはもう20年前ですね。
そこから20年で大きく変わりました。米国の増加が顕著です。
これは、2001年にアメリカを襲った同時多発テロ以降、「貧困がテロの温床になっている」という考えから、ODA予算を増加させているという背景があります。
こうした国内要因や国際情勢が、日本のODA実績を相対的に低下させたといえます。
GNI比0.7%ODA拠出掲げるが現実は?
国の経済規模に対して、どれぐらいの貢献をしているかを測る指標として「対GNI比」というのがあります。
GNIとは国民総所得のことで、国の経済規模を表すものです。
対GNI比とは、国の経済規模に対してどのくらいの割合をODAとして供与しているかを示す数値になりますね。
国際社会では、貧困削減や環境問題など地球規模の課題に対応するために、各国ともGNI比で0.7%のODA量を確保することが求められています。
米国は金額は大きいのですが、GNI比でみると、0.16%。評価としては難しいですよね。
日本は、0.28%で0.7%は達成していません。ただ、不景気、コロナなどの問題で、これを増やすのは容易ではないでしょう。。。
各国の国際協力を確認する際のポイント
各国の国際協力の概要を確認する際のポイントとして、以下3点が上がられます。
①各国の特徴が異なるため、まずは各国の特徴を理解すること
・実施機関の有無(省庁のみ、実施機関あり、さらには複数の実施機関がある場合も)
・支援の方法(スキーム)の違い(技術協力、無償資金協力、有償資金協力、民間投融資、保証等)
・重点分野や地域
②各国の援助戦略・方針は各国政府の外交政策に大きく左右されます(日本だと、「自由で開かれたインド太平洋戦略」なんていうのがありますね) 。
同盟国間では、同盟強化の観点から連携推進を政府等から 求められることもあります。
③各国の援助戦略は、もちろん各国の思惑(自国企業と使う、自国の技術のこだわりなど) にも大きく影響されます。
かつては、世界一のODA大国として君臨した日本ですが、今は世界4位です。
日本だけでいろいろやることには限界もあります。今後は、2030年のSDGs達成のために他の援助機関との連携も求められれますので、他の援助機関の特徴をしることは大切なことですね。
②主要な先進国 (米、英、仏、独)の援助政策や特徴
ここで伝統的な先進国である、米、英、仏、独を見ていきましょう。
米国

まず米国です。今やODA拠出額世界一位の大国です。
- 主要機関: 国際開発庁(USAID)
- 事業規模: 12,033百万ドル(≒1兆2,496億円)
- 役職員数: 3,551人
- 事務所数: 87拠点
- 援助対象国: 100か国以上
- 事業スキーム: 技術協力、無償資金協力、民間投融資(※)
※民間投融資に関しては、海外民間投資公社(OPIC)及びUSAIDの開発信用機関機能を集約した、新たな国際開発金融公社(USDFC)が2020年発足。
2017年1月に発足したトランプ政権は、「米国第一主義」の政策のもと、世界中の米国民の安定・安全・繁栄のために米国の安全保障、経済利益および価値を推進することを重視しています。
2018 年度の予算教書にて、外交および対外援助予算を前年比で 3 割削減を目指していましたが、議会超党派の反対により予算削減は覆されました。
重点分野として、⑴ 自由で開かれたインド太平洋地域、⑵ 長期的な開発に対する米国のコミットメント強化、⑶ 米国の道徳的および多国間リーダーシップの強化、⑷ 米国の安全保障と経済利益の促進、を掲げています。
英国

次は英国です。「貧困削減」を援助の基本目的として、貧困層への裨益(ひえき)を明確に打ち出してます。
- 主要機関: 国際開発省(DFID)→外務・英連邦・開発省(FCDO)(※1)
- 事業規模: 11,107百万ポンド(≒1兆5,772億円)
- 役職員数: 3,526人
- 事務所数: 36拠点
- 援助対象国: 優先33か国/5地域/開発パートナー3か国
- 事業スキーム: 技術協力、無償資金協力、民間投融資(※2)
※1:2020年9 月に国際開発省(DFID)を外務・英連邦省(FCO)と統合され、新たに外務・英連邦・開発省(FCDO: Foreign, Commonwealth and Development Office)が発足。
※2:英連邦開発公社(CDC)グループが、開発途上国の産業・生活インフラ支援のための投資・融資等への資金協力等を実施。
参考:英国政府サイト
2002年に成立した国際開発法を基本としています。
2015年11月に援助戦略の見直しを発表し、貧困撲滅という開発協力の目標を、英国の経済的・安全保障面での国益に一致させる方向性を明確にしました。
具体的には、①ODA計上の拡大によるGNI比ODA予算の0.7%国際目標達成の継続、②費用対効果の重視、③4つの優先分野の策定(平和・安全関連の予算の増額、危機対応や強靱性支援の強化、成長志向の支援政策の強化と「繁栄基金」による民間向けの出資・融資等の強化、極度の貧困の撲滅)、④DACのODA統計のルールの変革を挙げています。
英国はODAの対GNI比0.7%の国際目標を2013年から達成中です。EUから脱退したことで、今後の数字がどう動くのか、興味ありますね^^
フランス

次はフランスです。
- 主要機関: 開発庁(AFD)
- 事業規模: 14,123百万ユーロ(≒1兆7,832億円)
- 役職員数: 2,650人
- 事務所数: 85拠点
- 援助対象国: 115か国
- 事業スキーム: 技術協力、有償資金協力、無償資金協力、民間投融資(※)
※AFDグループ傘下のPROPARCOが実施。
同国「開発法」第1条には、仏の開発政策は発展途上国における持続可能な開発を経済・社会・環境・文化面で促進することが目的であると規定。
特に取り組みを進める10分野として、以下を掲げてます。
①保健・社会保護、②農業・食料安全保障と栄養、③教育・職業訓練 ④民間セクター・企業の社会的責任 ⑤国土の均衡ある開発、⑥環境・エネルギー、⑦水・衛生 ⑧ガバナンス・汚職対策、⑨人の移動・移民・人材育成、⑩貿易・地域統合。
また分野横断的な目的として、女性の自立支援および気候変動への対応を挙げています。
2018年に開催された国際協力・開発委員会(CICID)の新援助方針では、2022年までに対GNI比で0.55%に増やすとし、特に対アフリカの後発開発途上国(LDCs)への支援を強化するとしています。
ドイツ

次はドイツです。ドイツは主要機関が2つ、GIZとKfWがあります。
- 主要機関: 国際協力公社(GIZ)
- 事業規模: 2,944百万ユーロ(≒3,737億円)
- 役職員数: 7,079人
- 事務所数: 86拠点
- 援助対象国: 約120か国
- 事業スキーム: 技術協力、無償資金協力
- 主要機関: 復興金融公庫開発銀行(KfW Dev. Bank)
- 事業規模: 8,692百万ユーロ(≒1兆975億円)
- 役職員数: 6,705人
- 事務所数: 69拠点
- 援助対象国: 約70か国
- 事業スキーム: 有償資金協力、無償資金協力、民間投融資(※)
※KfWグループのドイツ投資開発公社(DEG)が途上国の民間部門への投融資を実施。
参考:GIZ 2019年年次報告書、KfW 2019年財務報告書、KfW 2019年Facts and Figures
開発協力を国際貢献・参画の最重要手段と位置付け、グローバルな開発課題に取り組んでいます。伝統的に、日本と同様二国間援助を重視し、民間企業、NGO等との連携に力を入れています。
重点分野としては以下を掲げています。
①世界全体における尊厳ある人生の実現、②自然環境の保全および持続可能な利用、③持続可能性および尊厳ある雇用に基づいた経済成長、④人権の尊重およびグッド・ガバナンスの要求・促進⑤平和構築および人間の安全保障の強化、⑥文化的・宗教的多様性の尊重および保護、⑦変革を実現するためのイノベーション、新技術およびデジタル化の活用、⑧新たなグローバル・パートナーシップおよび多様な主体とのパートナーシップの構築
私のこれまでの開発経験でも、ドイツは日本と同様に、技術協力=人材育成に非常に力を入れている印象があります。
③コロナ禍でも先進国はODA増額方向

最近のコロナ感染拡大後の先進国の援助トレンドはどうなっているのでしょうか。
主要先進国のODA予算はコロナ禍ですが、援助を強化するようで増額方向です。
- 米国:下院が659億米ドルの2021年度外交・対外活動関係予算配分法案(国際的なコロナ対策緊急予算含む)を可決(前年度比約15%増)。バイデン政権成立により対外援助増額の可能性もあります。
- 英国:コロナによる経済緊縮を理由に2020年ODA当初予算を減額しつつも、GNI比0.7%維持を表明してます。
- フランス:マクロン大統領就任時の目標(2022年GNI比0.55%)を上回り、2021年予算案は債務救済分を含め204億米ドル、対GNI比で0.69%となります。
- ドイツ:ODA予算をコロナ対策支援を反映して増額する見通し(2020年・21年ともに当初予算128億米ドルを146億米ドルに増加)。なお、2021年ODA予算(12月採択予定で審議中)は225億米ドルの見込み。
各国、コロナで自国経済は厳しい状況ながら、ODA予算はしっかり維持、もしくは増額ですね。
まとめ:各国に特徴があり、コロナ禍でもその方向性は変わらない

記事のポイントをまとめます。
- 先進国の援助総額は増加。日本は2000年をピークに減少傾向。
- 先進国として、米国、英国、フランス、ドイツはそれぞれ特徴があり。
- コロナ禍でも、援助強化、金額も増額方向。
このようなイメージでしょうか。結論として、各国の援助方針に沿って、コロナ禍でも支援を上乗せしているということですね。
国際協力の業界を理解するうえで、伝統的な先進国の援助方針を理解しておくことは、これまでとそしてこれからの援助動向を予測するうえで役に立ちます。折を見てこの記事内容もアップデートしていきたいと思いますので宜しくお願いします。



